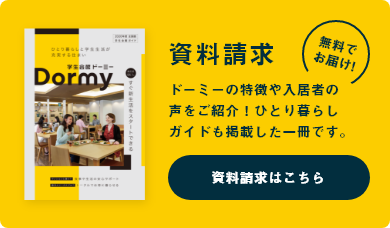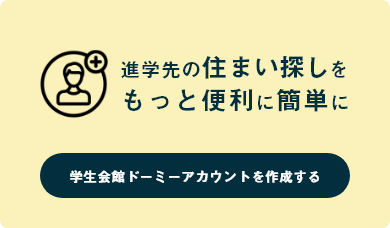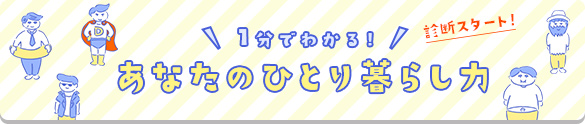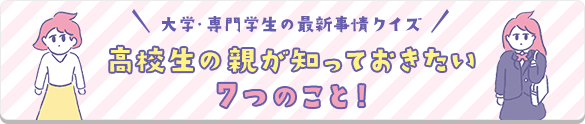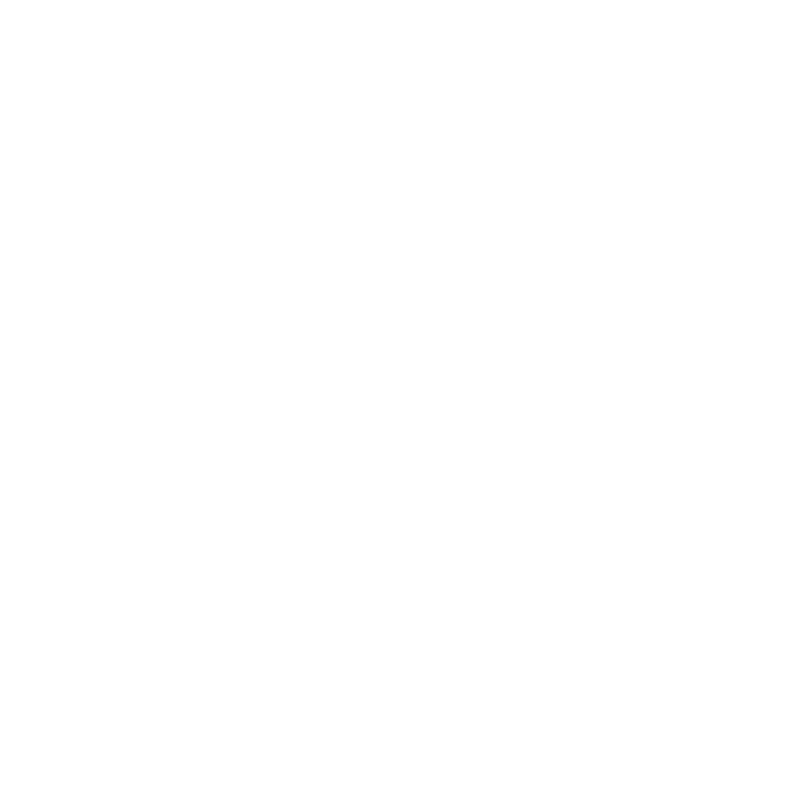専門学生と大学生はどっちが忙しい?学生生活の実態と時間の使い方を徹底比較

学費や就職率といった観点での比較に比べて、実際の学生生活の「忙しさ」という視点は気になるけれど分かりにくい部分かもしれません。
この記事では、専門学校と大学それぞれの「忙しさ」の特徴や時間の使い方について詳しく解説します。自分に合った進路選択の参考にしてくださいね!
⏱この記事は約10分で読めます
専門学校と大学の授業スケジュールの違い
専門学校と大学では、授業の組み方や1日のスケジュールが大きく異なります。それぞれの特徴を理解して、入学後の生活をイメージしてみましょう!
専門学校の一日と一週間のスケジュール例
専門学校の授業スケジュールは、多くの場合「高校の延長線上」といった印象で、朝から夕方まで決められた時間割に沿って授業が組まれていることが一般的です。
(例)美容系専門学校の1週間のスケジュール
月曜〜金曜:9:00〜16:30(昼休み1時間)
午前中:座学(色彩理論、接客マナーなど)
午後:実技・実習(カット練習、メイク実習など)
このように、1日のほとんどが授業で埋まっており、高校生活から比較的スムーズに移行できる時間割となっています。一方で、自由時間は限られることになります。
大学の一日と一週間のスケジュール例
大学の時間割は、学生自身が組み立てる自由度が高いのが特徴です。必修科目は決まっていますが、それ以外は自分の興味関心に合わせて選択できます。
(例)一般的な文系学部の1週間のスケジュール
月曜:1限(8:50〜10:30)、2限(10:40〜12:20)、5限(16:20〜18:00)
火曜:授業なし
水曜:3限(13:00〜14:40)、4限(14:50〜16:30)
木曜:2限、3限
金曜:1限、4限
このように「すきま時間」が多く、中には「大学は週3日だけ」という学生もいます。ただし、この「空き時間」をどう使うかによって、充実度や忙しさが大きく変わってきます。
授業時間数と密度の比較
両者を比較すると、単純な「時間数」では専門学校の方が多い傾向にあります。
専門学校は週25〜30時間程度の授業、みっちり詰まったカリキュラムで、1日の授業数は4〜6コマが一般的です。
一方の大学は、学部によりますが、週10〜20時間程度の授業を自分で組み立てるため、1日の授業数は0〜5コマと自由度が高いものになります。
ただし、これは「拘束時間」の比較であり、実際の勉強量や忙しさとは必ずしも一致しません。授業外での学習時間や課題の量も考慮する必要があります。
専門学校の「忙しさ」の特徴
専門学校の忙しさには独特の特徴があります。特に実践重視の教育スタイルが学生生活にどう影響するのかを見ていきましょう。
実習・演習中心のカリキュラムがもたらす忙しさ
専門学校の最大の特徴は「実習・演習」の多さです。
例えば調理師専門学校なら毎日の調理実習や包丁の手入れ、デザイン系専門学校なら作品制作やポートフォリオ作り、医療系専門学校なら日々の現場研修や実技試験対策など。
これらの実習は授業時間内だけでは終わらないことも多く、放課後や休日に練習や準備をする必要がある場合も。特に技術が求められる分野では、反復練習が欠かせません。
資格取得に向けた学習負荷
専門学校のもう一つの特徴は、資格取得を重視していることです。多くの専門学校では、在学中に複数の資格取得を目指します。
例えば、情報系専門学校では、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、Oracle認定Java資格、Cisco技術者認定資格など、業界で求められる資格の取得をカリキュラムに組み込んでいることが多いです
これらの試験対策のための勉強時間も必要となります。
課題や実技練習の量と質
専門学校の課題は「実践に直結する」ものが多いのが特徴です。
例えばファッション専門学校なら一着の服を完成させる、製菓専門学校なら新しいスイーツのレシピを開発する、アニメーション専門学校なら短編アニメーションの制作など、これらの課題は時間がかかるだけでなく、クオリティも求められます。「提出すればOK」ではなく、実際に通用するレベルの完成度が期待されることが多いのです。
大学の「忙しさ」の特徴
大学生活の忙しさは、専門学校とはまた異なる特徴を持っています。自由度が高い分、自己管理が求められる側面もあります。
自己管理が求められる学習スタイル
大学の学習の特徴は「自主性」にあります。授業時間は専門学校より少ないものの、授業外での学習が前提となっています。
レポート作成は3000〜5000字程度の論述が一般的で、時間がかかります。文献研究では図書館やオンラインデータベースで資料収集を行う必要もあるでしょう。各講義の予習・復習も、授業1コマにつき2時間程度の自習が理想とされています。
特に理系学部では、実験レポートの作成に何日もかかることも珍しくありません。また文系学部でも、一つのレポートに何十冊もの参考文献を読み込むことが求められるケースもあります。
サークル活動や課外活動の充実度
大学生活の特徴として、サークル活動や部活動の存在も見逃せません。
専門学校にも同様の活動はありますが、大学のサークル活動は特に活発で、「大学はサークルが本業」と言われるほど、サークル活動に情熱を注ぐ学生も少なくありません。
こうした活動が「楽しい忙しさ」を生み出していることも大学生活の特徴です。
研究活動やゼミにかける時間
大学の後半(主に3〜4年次)になると、ゼミ(研究室)に所属して専門的な研究活動を行うことになります。この時期になると忙しさのレベルが変わることも。
週に1回はゼミ発表の準備をし、卒業論文のための調査・実験、教授との個別ミーティングを重ねていきます。特に理系の研究室では、「研究室に泊まり込み」というほどの忙しさになることも。
アルバイトと学業の両立は可能?
学生生活の忙しさを語る上で避けて通れないのが「アルバイト」の存在です。専門学校生と大学生では、アルバイト事情にどのような違いがあるのでしょうか。
専門学校生のアルバイト事情
専門学校生のアルバイト状況は、学ぶ分野によって大きく異なります。
学んでいる分野に関連したアルバイト(美容系ならアシスタントなど)をする方も多いです。授業の拘束時間が長いため、週2〜3日、短時間のシフトが一般的。学校推薦のアルバイト先がある場合もあります。
「学んでいることをすぐに活かせる」という点で、専門的なアルバイトができるのは専門学校生の強みです。ただし、授業や課題が多いため、アルバイトに使える時間は限られます。
大学生のアルバイト事情
大学生のアルバイトは、時間の融通が利きやすい特徴があります。
週3〜4日、1日5時間程度シフトに入るのが一般的で、長期休暇中は週5日以上フルタイム勤務も可能です。塾講師、家庭教師、カフェスタッフなどが人気ですが、選択肢も幅広いでしょう。
大学生の約7割がアルバイトをしているというデータもあり、月に5〜8万円程度の収入を得ている学生が多いようです。ただし、アルバイトに時間を取られすぎて学業がおろそかになるケースもあるため注意が必要です。
★ドーミーラボでは専門学生と大学生のアルバイト探しに関するヒントについて発信しているので、以下の特集記事もぜひ覗いてみてください。
分野別・学科別の忙しさの違い
専門学校も大学も、学ぶ分野によって忙しさのレベルが大きく変わります。どの分野が特に忙しいのか見ていきましょう。
専門学校の忙しい学科
専門学校の中でも、特に忙しいと言われる学科は、
医療系(看護、理学療法など):臨床実習と国家試験対策で超多忙
美容・理容系:技術習得に膨大な練習時間が必要
調理師・製菓:毎日の実習と体力勝負の実技
アニメ・マンガ・ゲーム:作品制作の締切に追われる日々
音楽・演劇系:練習・レッスンが生活の中心に
です。
特に医療系は学習内容が多く、専門的な知識と技術の習得に加えて臨床実習もあるため、非常に学習量が多い傾向にあります。看護学校の学生からは「課題と実習の両立で時間管理が大変」という声も聞かれます。ただ、その分やりがいも大きく、将来に直結する学びが得られる点が特徴です。
大学の忙しい学部・学科
大学でも、学部や学科によって忙しさは様々です:
医学部・歯学部・薬学部:6年間休みなく勉強の連続
理系学部(特に実験系):レポート作成と実験で徹夜も
芸術系学部:作品制作に没頭する日々
教育学部:教育実習や教員採用試験対策で多忙
法学部(法科大学院進学志望):司法試験を見据えた勉強量
特に医学部は「大学のハードさランキング」で常に上位。理系学部では実験レポートの作成に追われる日々が続き、一つの実験レポートに20時間以上かかるようなことも。文系学部でも、法学部では判例の読み込みや膨大な暗記が必要ですし、教育学部では教育実習や指導案作成に多くの時間を費やします
学部によって忙しさの質が異なるのが大学の特徴です。
自分の学びたい分野はどうなの?
自分が目指す分野の「忙しさ」を事前に知るには、以下の方法が有効です:
オープンキャンパスで在校生に聞く:リアルな声が聞ける貴重な機会
SNSで同じ分野の学生をフォロー:日常の様子がわかる
卒業生のブログや体験談を読む:長期的な視点で参考になる
学校説明会で時間割の例を確認する:実際の拘束時間がわかる
特にオープンキャンパスは必ず参加しましょう!パンフレットだけでは分からない「実際の忙しさ」や「学生生活の実態」を知るチャンスです。在校生や先輩に積極的に質問することで、入学後のミスマッチを防げます。
オープンキャンパスの過ごし方や注意点については、以下の特集記事もぜひ読んでみてください!
充実した学生生活を送るためのアドバイス
専門学校でも大学でも、「忙しい」と感じるかどうかは時間の使い方次第。充実した学生生活を送るためのアドバイスをご紹介します。
時間管理スキルを身につけよう
効率的な時間管理は、学生生活を充実させるための重要なスキルです。
時間管理の基本として、手帳やカレンダーアプリなどのツールを活用して予定を可視化することが有効です。頭の中だけで管理しようとすると限界があるため、自分に合った方法で予定を「見える化」しましょう。
また、タスクに優先順位をつける習慣も大切です。重要度と緊急度を基準に取り組むべきことを判断できると効率が上がります。さらに余裕を持ったスケジュール管理も効果的で、「締切の2日前」を実際の締切と考えることで、突発的な出来事があっても対応できます。
時間管理は一朝一夕で身につくものではありませんが、少しずつ習慣化することで確実に生活の質が向上します。
一人暮らしで時間を有効活用するコツ
住環境も時間の使い方に大きく影響します。特に専門学校や大学進学を機に一人暮らしを始める方も多いでしょう。
★効率的な生活環境作りのポイント
通学時間を最小限にする:学校近くの物件を選ぶ
食事の時間を効率化する:簡単な自炊レシピを覚える
身の回りの整理整頓を習慣化:物を探す時間のロスをなくす
学習環境を整える:集中できる空間づくり
生活リズムを一定に保つ:睡眠の質が時間の質を左右する
これらのポイントを考えると、実は学生寮も時間管理の観点からとても魅力的な選択肢です!
多くの学生寮では食事が提供されるので自炊の手間が省け、洗濯や掃除の負担も軽減されることが多いため、その分の時間を学業や趣味に充てることができます。また学校に近い物件が多く通学時間も短いくなるので、朝の貴重な時間を有効活用できるというメリットも。時間を大切にしたい方には、学生寮という選択肢も検討してみる価値がありますよ!
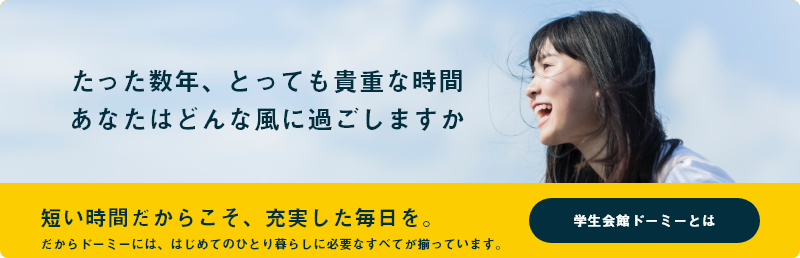
無理なく「忙しい」を楽しむメンタリティ
最後に大切なのは、心の持ち方です。同じ「忙しさ」でも、捉え方次第で充実感は大きく変わります。
小さな達成感を大切にし、日々の進歩を実感することで、モチベーションを維持できます。「やらされている」と感じるのではなく、「自分がやりたいこと」として意識を転換することも効果的です。また、適度な休息とリフレッシュの時間を確保し、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨することで、忙しさの中にも楽しさを見出せるでしょう。
自分が本当に打ち込めることを見つけることが、充実した学生生活の鍵かもしれません。
自分に合った「忙しさ」を選ぼう
専門学校と大学、どちらが忙しいかという問いに対する一概な答えはありません。どちらも学ぶ分野や自分の取り組み方によって「忙しさ」は変わってきます。
専門学校は拘束時間が長く、実習や資格取得に向けた学習が中心。大学は自由度が高い分、自己管理能力が問われます。どちらにもメリット・デメリットがあり、どちらが「忙しい」かではなく、自分に合った「忙しさ」を選ぶことが重要です。
忙しさは「充実」と同義ではありません。時間がたくさんあっても無駄に過ごしては意味がなく、忙しくても計画的に過ごせば充実した学生生活を送ることができます。自分が本当に打ち込めることを見つけ、充実した学生時代を過ごしてください!
関連記事
専門学校と大学の学費を徹底比較!どちらがお得?進路選択のミカタになる情報を解説