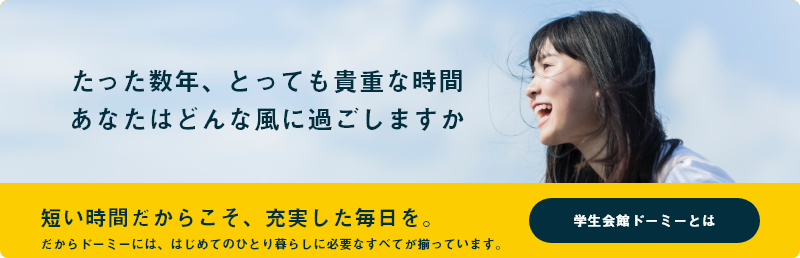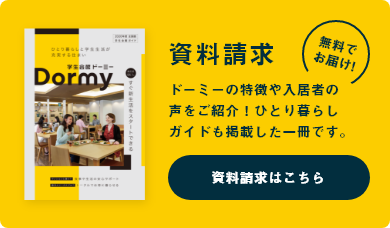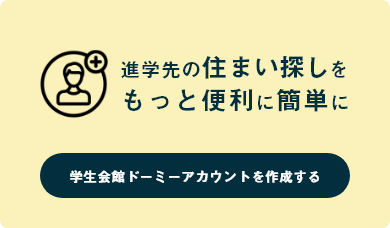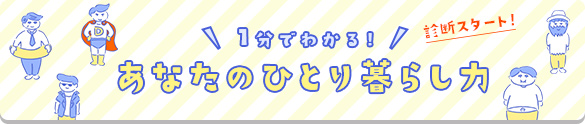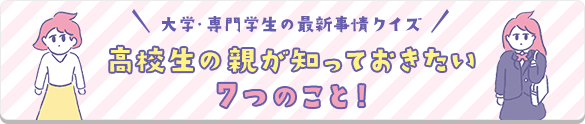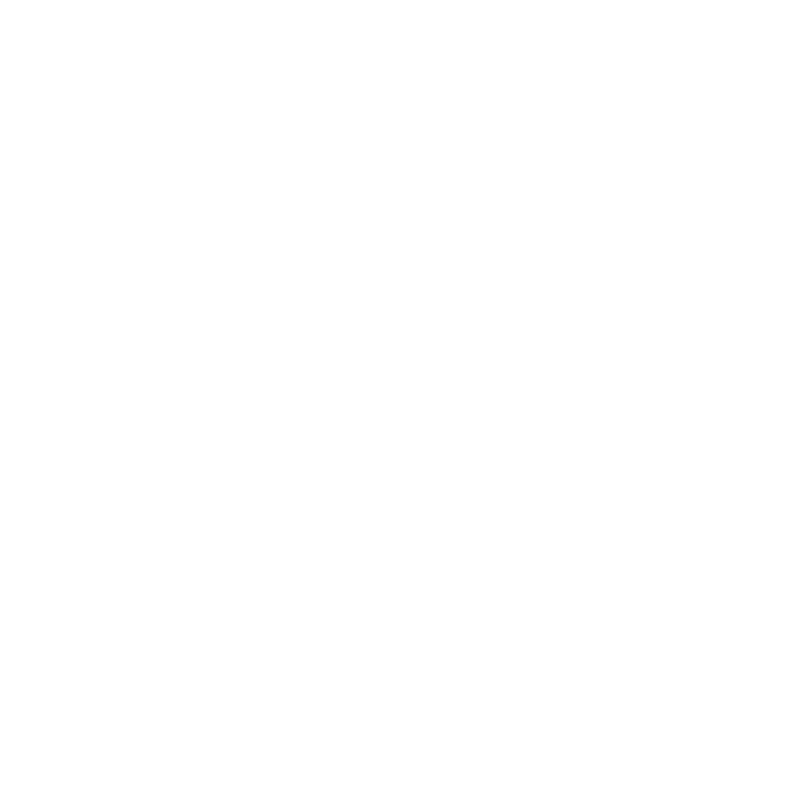コロナの影響で奨学金を巡る環境はどう変わったの?情報収集のコツ【奨学金アドバイザーが詳しく解説】
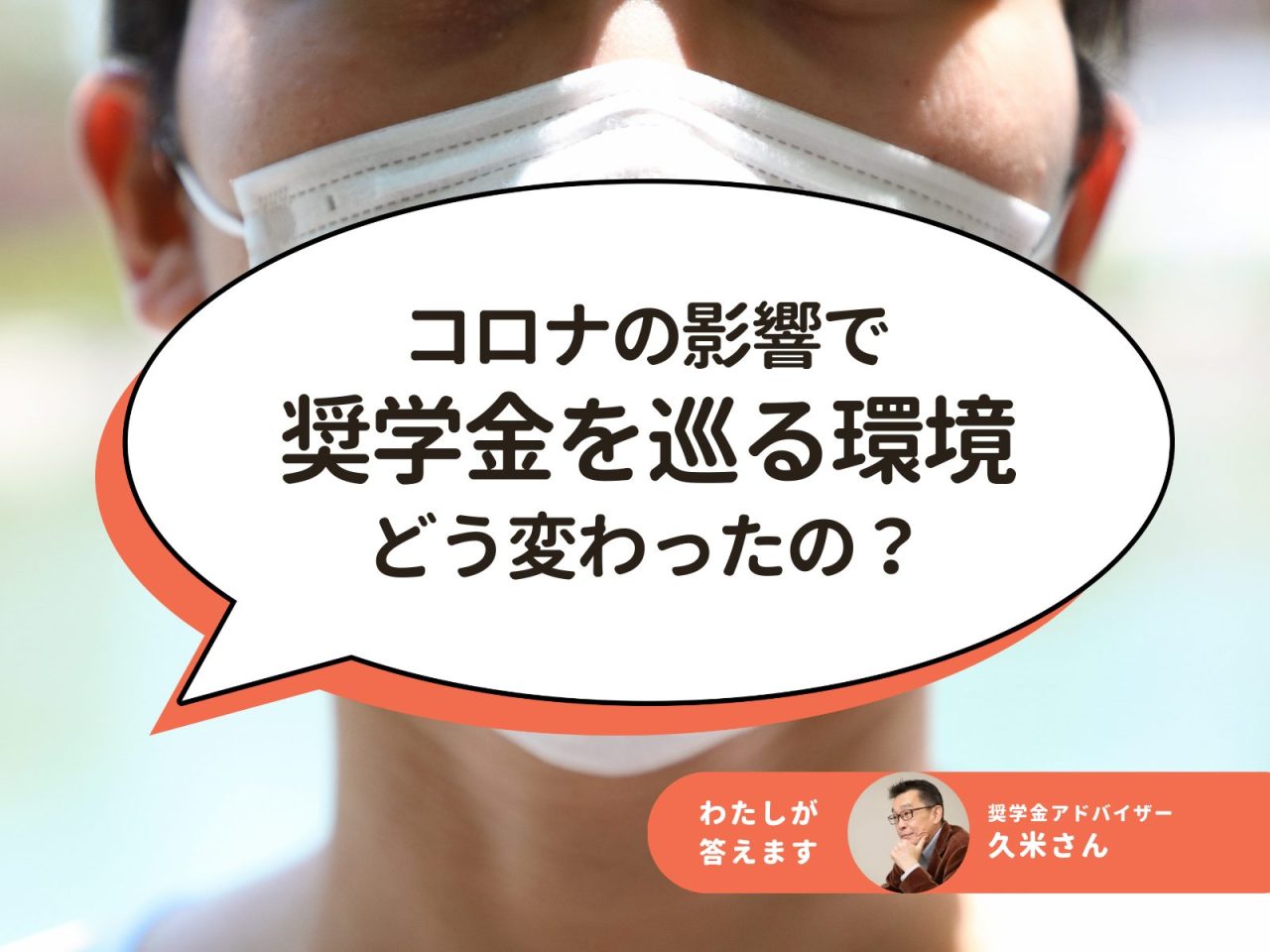
⏱この記事は約3分で読めます

コロナ禍で大学の動き方も変わる中、奨学金を巡る環境はどう変わったの?
コロナ云々という話ではありませんが、来年から変わるのが、給付型奨学金の対象が広がります。第一・第二・第三区分まで家庭の収入環境に応じてあったのが、第四区分が作られます。世帯年収が600万円くらいの、いわゆる中間家庭。そこへ対象が広がるのが大きな変化の1つです。
また、同じく来年度から始まるのが大学院生の出世払い制度。具体的にどうなっていくかは詳細はわからないのですが、学費の後払い制度と思ってもらってよいでしょう。国が想定しているのが「年収300万円未満であれば返済しなくていい」ということなので、それを越えたら出世払いの対象になるという仕組みです。
2024年度からの変更点でもうひとつ気になるのが、貸与型奨学金の家計基準の算定方式の変更です。簡単に言うと、給付型奨学金と同じく保護者の住民税情報をもとにした算定方式に統一されるというものです。
日本学生支援機構の奨学金には、高校時代に申込む予約採用と大学入学後に申込む在学採用の2つの申請方法があります。
その家計基準の審査では、保護者の収入から一定額が控除される仕組みがあり、在学採用の方がメリットが大きかったのですが、次年度からの制度変更の影響で、そのメリットが弱まるかも知れません。
状況が変化する中での情報収集のコツは?
学生が正しく情報収集ができる環境を整備するというは、大きな課題のひとつです。
学生支援機構の奨学金の相談窓口はそれぞれの在籍学校です。高校で申し込む時には高校。卒業するまでは大学が窓口。学生支援機構の相談センターもありますが、結果的にたらい回しにあってしまうケースが多いという声を聞きます。
20年前と比べて、奨学金制度はかなり複雑な仕組みになりました。また、家庭の状況も様々なので相談内容も多岐に渡るでしょう。日本学生支援機構の立場からすれば、限られた予算と人員の中での体制整備という限界もあると想像します。
そういう意味でいうと、本人のリテラシーも重要になってきます。ネットで調べたり、案内書をしっかり読み込むなど。最低限度、そこは基本としてやっていかなくてはならない。こうしたら安心だよというのが今は無い、その状況自体が課題と言えるかもしれません。
一番詳しい情報を持っているのは、やはり大学や専門学校の奨学金担当職員です。実例も知っているし、彼らには1000ページを越える手引書が提供されています。奨学金に関する経験と情報量が高校とは大きく違うため、何かわからないことがあれば、大学や専門学校の職員に相談するのがいいかもしれません。
この記事の監修者:奨学金アドバイザー・久米忠史

この記事の監修者:奨学金アドバイザー・久米忠史(くめ ただし)
株式会社まなびシード 代表取締役。2005年頃から沖縄県の高校で始めた保護者・高校生向けの奨学金ガイダンスが「わかりやすい」との評判を呼び、現在では高校だけでなく全国各地で開催される進学相談会や大学のオープンキャンパスなどで毎年150回以上の講演を行う。2009年には進学費用対策ホームページ「奨学金なるほど!相談所」を開設。