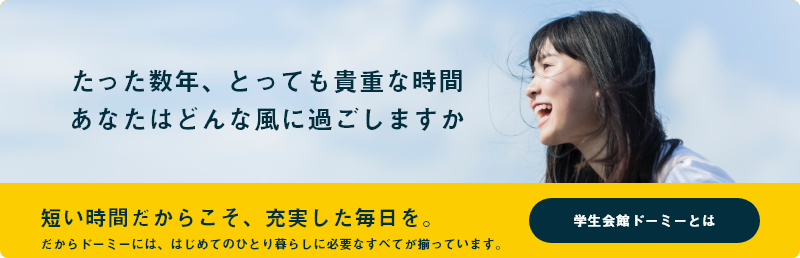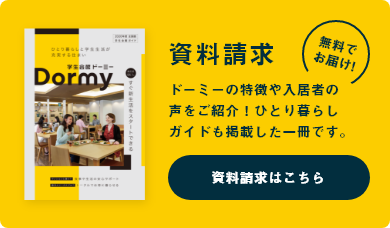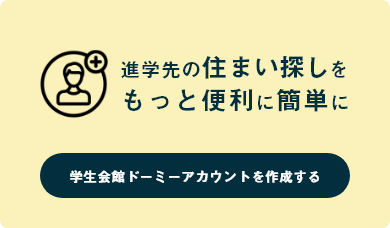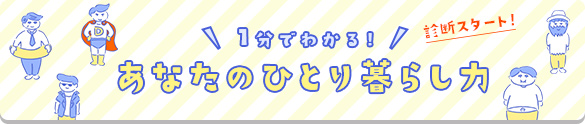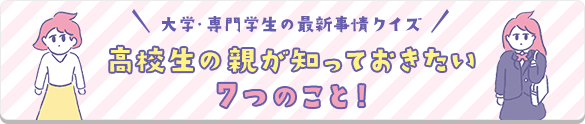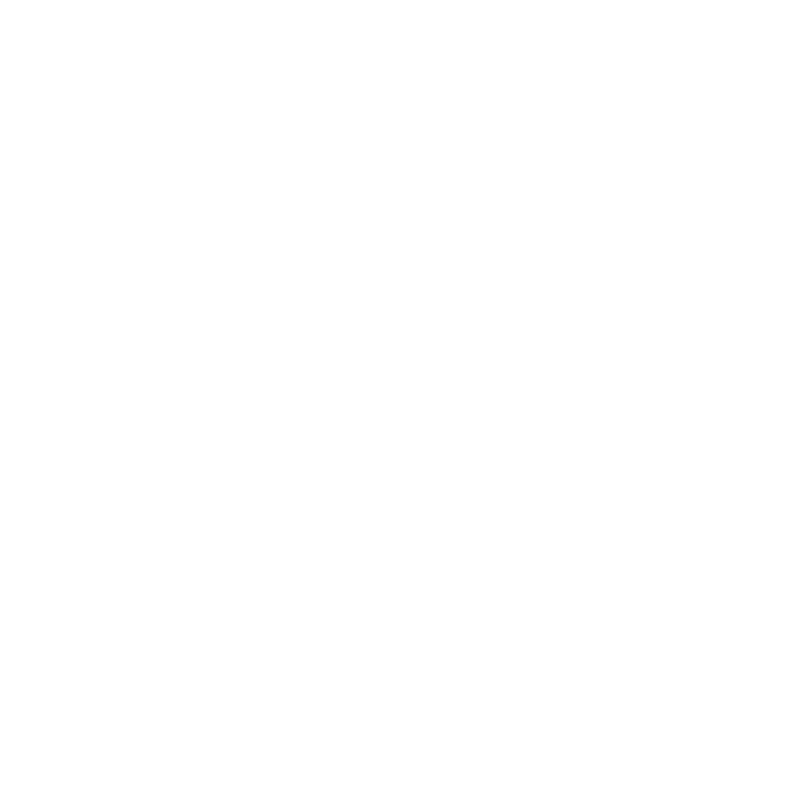これからの時代に重要スキルになる「コミュニティマネジメント」
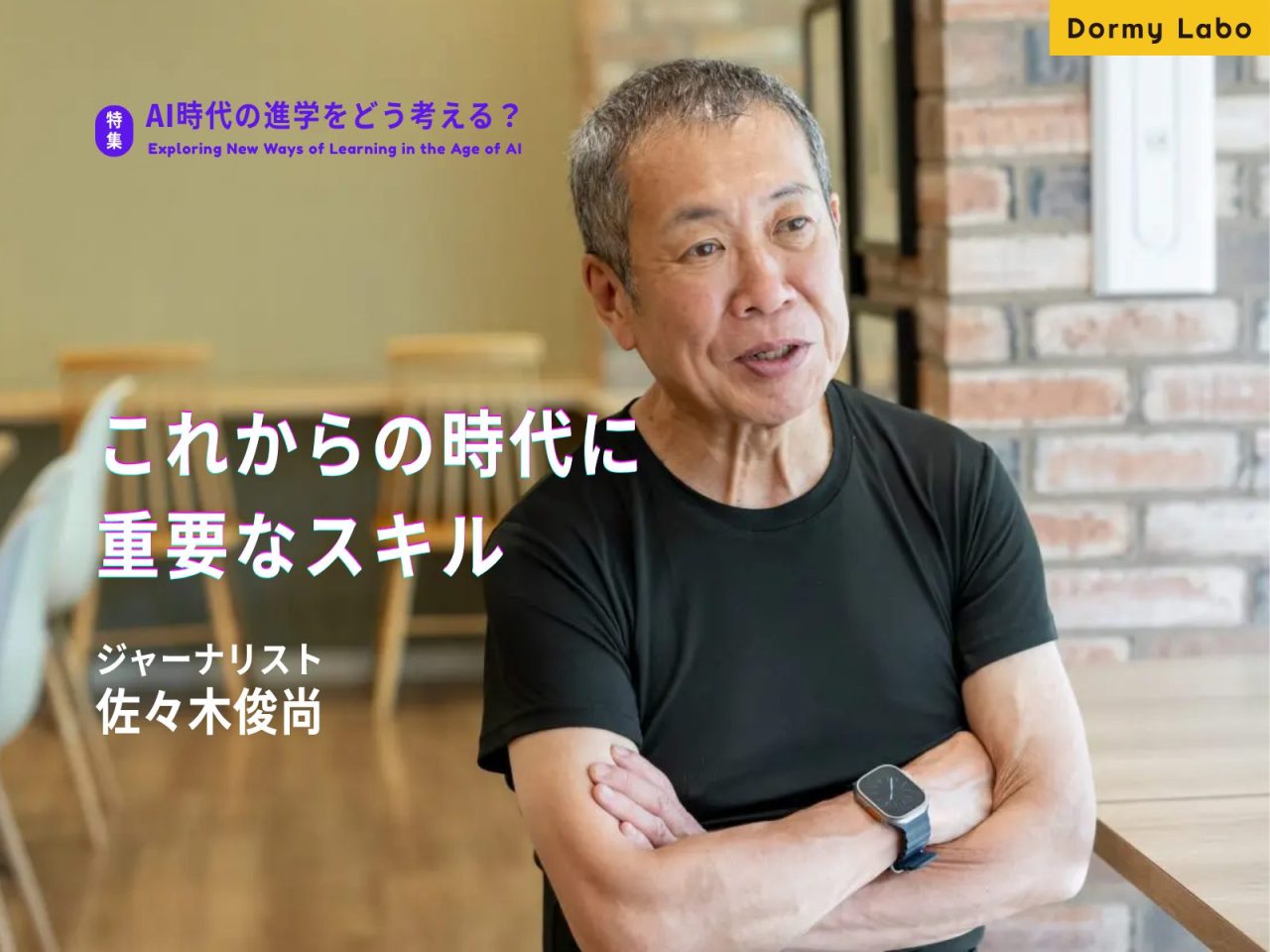
その専門的な見識を持つ佐々木俊尚さんに、前回記事から、ドーミーラボでは、多くの読者が気になる「これからの大学・専門学生に求められることは何か?」をお伺いしています。
今回は、人との出会いがますます重要になる中で、これからの時代により求められる「コミュニティ」についてお話いただきました。
⏱この記事は約3分で読めます
インターネットの次に来るのは「小さなコミュニティ」
「今の若い人たちは、同じ趣味や関心を持つ仲間をネットで見つけるのは自然にできるようになってきています。だから学校のような“無理やりのコミュニティ”に所属する必要がない、という側面もあるんです。でも逆に、共感できない人とどう関わるかとか、”貸し借り”のような曖昧な関係を保つことは難しくなっている。」
佐々木さんは、こうした状況を“次の課題”と捉えています。
「アメリカのメディアでも言われていますが、インターネットの次は“小さなコミュニティ”の時代になるだろうと。人と人の関わりには必ず不愉快なことも起こる。でも多様性とは“みんな仲良くすること”ではなく、“不愉快を我慢すること”なんです。そこでどう気持ちよく生きていけるかが問われていると思います。」
住まいがコミュニティを生み出す可能性:“摩擦”を取り戻す
住まいの在り方についても、佐々木さんはこう語ります。
「昔の日本の家には“半公共空間”がありました。玄関の土間や縁側で、近所のおばあちゃんと立ち話するような場です。ところが産業革命以降、工場労働者を大量に都市へ集める中で、公共とプライベートがきれいに切り分けられてしまった。結果として、コミュニティがなくなったんです。」

「だからこそ、完全にワンルームで閉じるのではなく、共有リビングやキッチンのように“摩擦”が生まれる場が必要なんです。僕が取材したコレクティブハウス(※)では、住人が持ち回りで食事をつくる仕組みがあって、料理が得意でない人も“今日は肉じゃがの日だな”とみんなで笑いながら受け入れていた。こういう“気持ちのいい摩擦”をどうデザインするかが大切なんですよ。」
※コレクティブハウス:集合住宅の形態の一。独立した居住スペースの他に、居間や台所などを共同で使用できるスペースを備えたもの。住民同士の交流や、子育て・高齢者などの生活支援に有効とされる。(出典:Weblio)

学生寮やシェアハウスは、まさにその実験場といえるかもしれません。
コミュニティを運営する難しさ
佐々木さん自身も、コミュニティの運営に挑戦した経験があります。
「松浦弥太郎(※)さんと一緒に有料コミュニティを4〜5年ほど運営していたんですが、本当に難しかった。最初は盛り上がっても、常連が強くなりすぎて新参者が入りにくくなる。そうなると少しずつ人数が減っていく“負の曲線”に勝てないんです。」
※松浦弥太郎:エッセイスト。クリエイティブディレクター。「暮しの手帖」前編集長。

「じゃあどうやって新しい人を呼び込み続けるのか? これはまだ社会全体でも研究され尽くしていません。だから“コミュニティマネジメント”はこれからの時代の重要なスキルになると思います。」
小さな衝突や不便をどう調整し、居心地のよい場をつくるか──これから社会に出ていく学生にとって欠かせない学びになるはずです。
ドーミーラボ編集部が感じたこと
佐々木さんのお話で印象的だったのは、「コミュニティマネジメントがまだ研究されつくされていない分野である」という点です。多くの人が必要性を感じながらも、具体的な方法論はまだ確立されていない。だからこそ、この領域には大きな可能性が広がっていると言えます。
そして、その実験と実践の場として、学生寮やシェアハウスは非常にユニークな存在だということです。日常的に“摩擦”や“不便さ”が生まれやすい共同生活の場だからこそ、コミュニティをどう運営し、どう居心地をつくるかが試される。ここでの経験は、社会に出た後の大きな財産になる可能性を示唆されたかと思います。
プロフィール
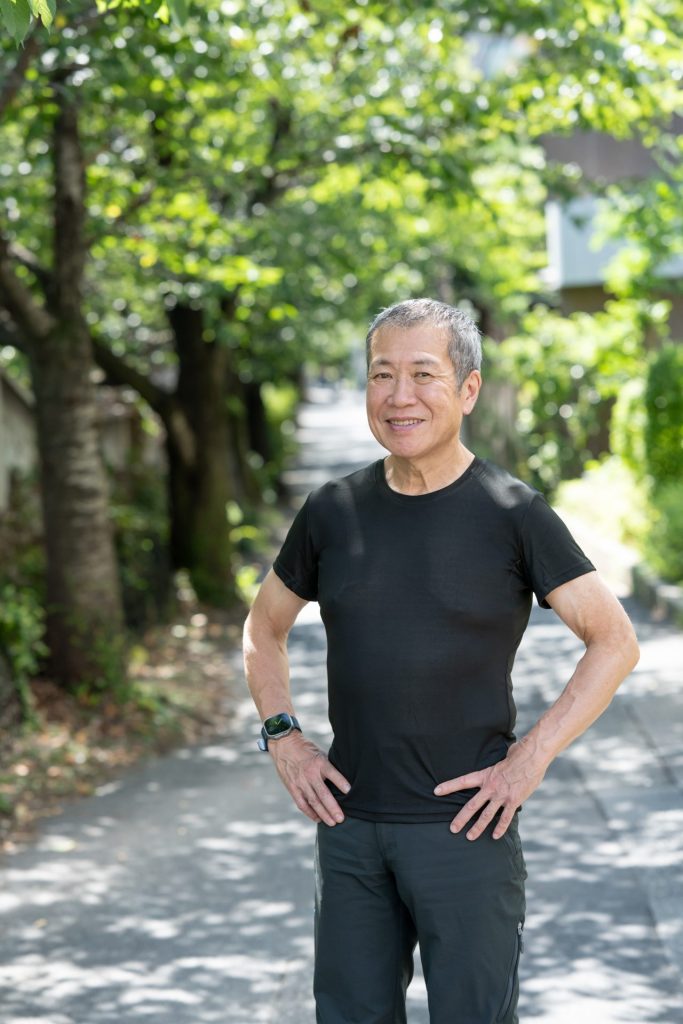
佐々木俊尚(ささき・としなお)
1961年兵庫県生まれ。早稲田大学政治経済学部中退。毎日新聞記者、『月刊アスキー』編集部を経て、2003年よりフリージャーナリストとして活躍。ITから政治、経済、社会まで幅広い分野で発言を続ける。現在は東京、軽井沢、福井の3拠点で、ミニマリストとしての暮らしを実践。著書に『レイヤー化する世界』(NHK出版新書)、『そして、暮らしは共同体になる。』(アノニマ・スタジオ)、『時間とテクノロジー』(光文社)など。
https://x.com/sasakitoshinao
関連記事
-
保護者におすすめ! 
【業界のプロに聞く】学生の住まい選び、2026年の新常識。「家賃の安さ」だけで選ぶと後悔する? 退学リスクも下げる“正しい投資”とは。
2026.02.05
-
高校生におすすめ! 
「生産性のない時間」こそが、自分を助けてくれる。——文筆家・岡田悠が語る「人生という旅」の歩きかた【連載・夢中人 Vol.11】
2026.01.19
-
高校生におすすめ! 
「人生は『泥縄』や。とりあえず引っ張れ!」先が見えない時代こそ面白く。―高木 秀章さん(塾長・学習塾経営)【連載・夢中人 vol.10】
2025.12.23
-
高校生におすすめ! 
大学生活で重要なのは“人脈”と“他者との出会い”
2025.11.17