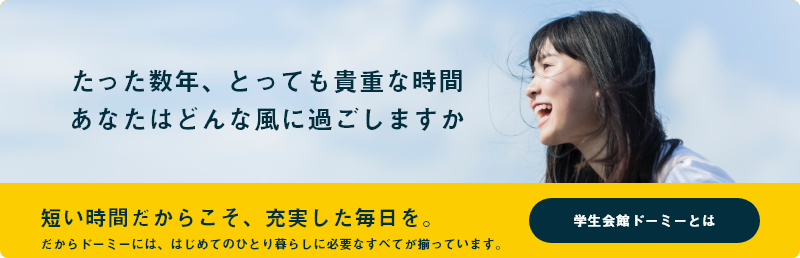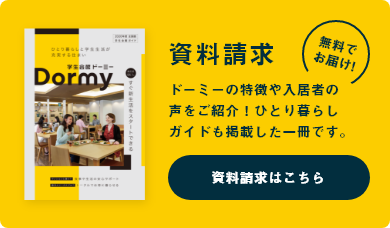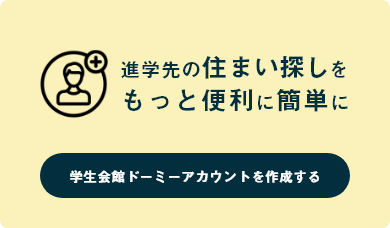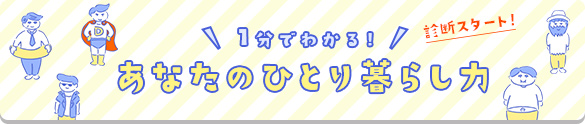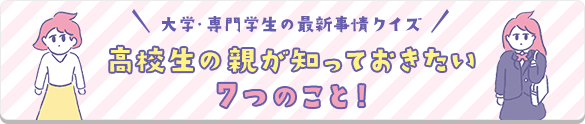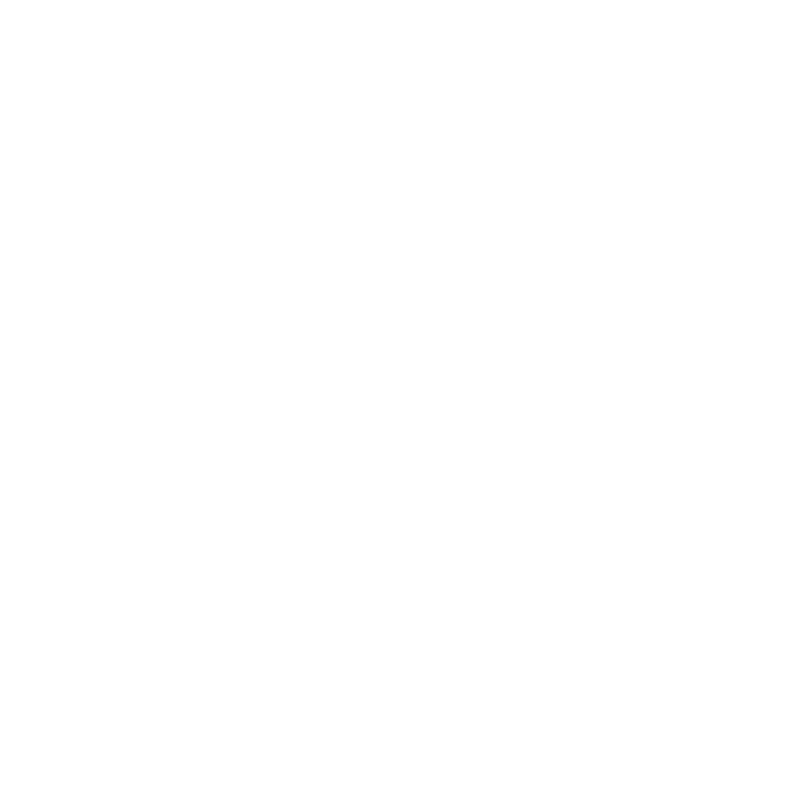大学生活で重要なのは“人脈”と“他者との出会い”
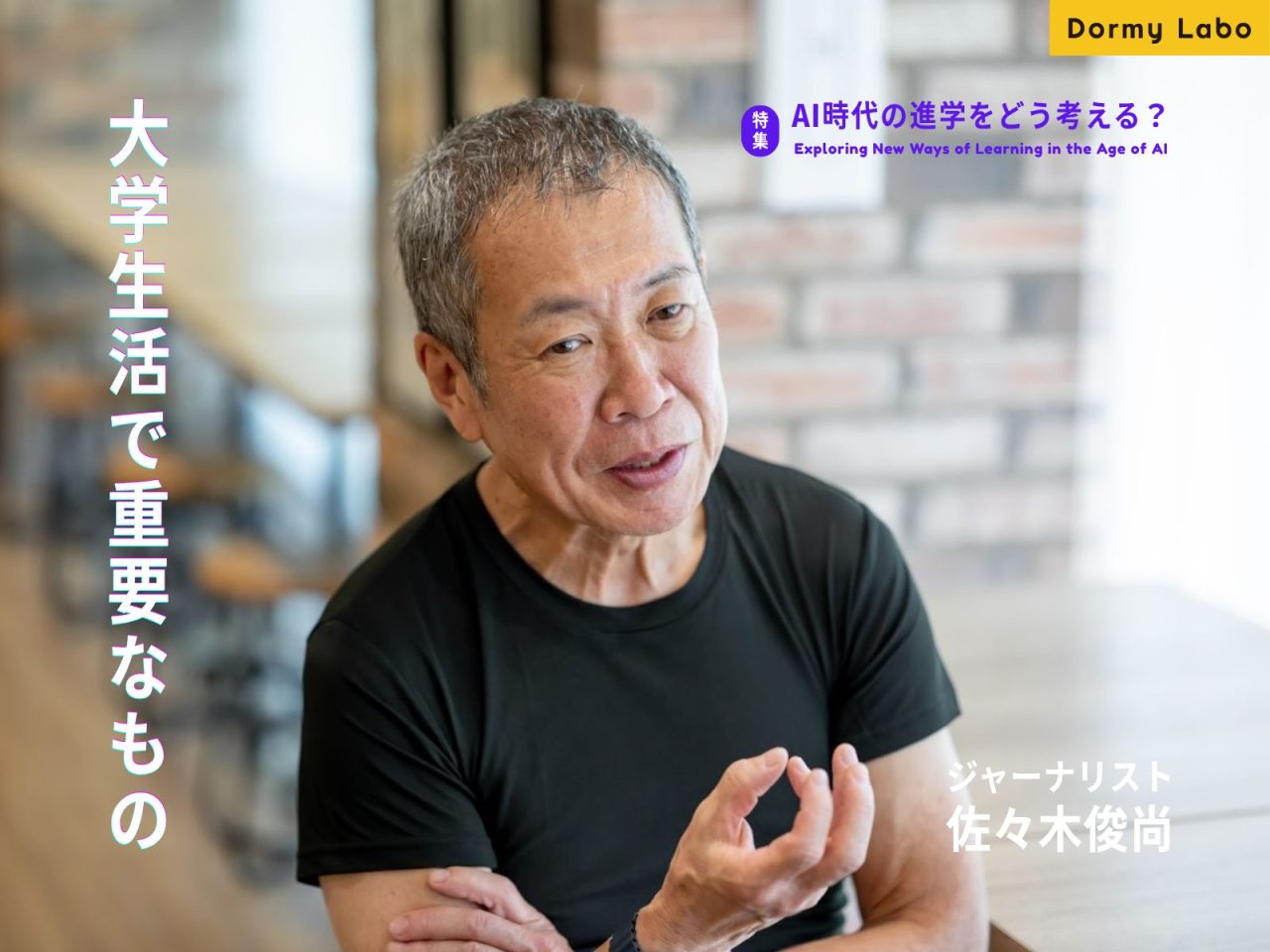
ITから社会、暮らしまで幅広く発信を続けるジャーナリスト・佐々木俊尚さんに、「これからの大学生に求められる力」についてお話を伺いました。
⏱この記事は約3分で読めます
「大学の本当の価値は“授業”ではなく“人脈”にある」
「日本の大学の学士レベルで受けられる教育って、正直言って大したものではないんです。本当に真面目に学問をやるのなら大学院に行くべきでしょう。じゃあ、学部で大学に通う意味は何か?――授業そのものではなく、そこで得られる人脈の方が大きいんです。」
佐々木さんは、慶應義塾大学を例に挙げます。
「慶應の人たちって、人脈の作り方がとても上手なんです。特に幼稚舎から上がってきた学生たちのつながりは極端に強い。卒業後も起業の資金を出してもらったり、創業メンバーを紹介してもらったり、あるいは相談役やメンターになってもらったり。大学の授業以上に、人脈が社会に出てからものすごい力を発揮しているんです。」
「普通の大学では、そこまで人脈が強く結びつかないことも多い。でも学生団体や任意団体の活動に参加しながら、自らネットワークを作ろうとする学生は増えています。授業以外の活動こそが、大学生活の大きな価値なんです。」

さらに佐々木さんはこう続けます。
「自分にないものを持っている人と仲良くすること。これは大学で特に大事です。例えばデザイナーとエンジニアと営業が一緒になれば、それぞれが欠けている部分を補い合って、新しい会社だって作れる。僕自身もコワーキングスペースの黎明期に、そうした“出会い”からプロジェクトが生まれる場面をたくさん見てきました。」
ただし、そのためには環境を活かす力も必要だと言います。
「小中高のクラス社会は閉鎖的で、そこでいじめも起きやすい。大学に入るとそうした“閉じたクラス”が消えるので、本当はいろんな人と出会うチャンスなんですよ。ところが、多くの学生はサークルや団体に入らず、教室と自宅を往復するだけになってしまう。せっかくの風穴が開いた場所を活かしていないのは、本当にもったいないと思います。」
「雑談力」こそ人とつながる第一歩

では、どうすれば他者との出会いをつなげていけるのか。
「僕が思うのは、“雑談力”がすごく大事だということです。相手に『何をしているんですか?』と聞いてみる。それに興味を持って、『それってどんな活動なんですか?』と掘り下げていく。そうすると会話が自然に広がるんです。知識をひけらかしたり、逆に天気の話ばかりするのではなく、相手にインタビューするように接してみると、仲良くなれるんですよ。」
ドーミーラボ編集部が感じたこと
佐々木俊尚さんの言葉から浮かび上がるのは、学部での大学生活の核心が「授業」ではなく「出会い」にあるという視点です。
人と出会い、そこからネットワークを築く力は、社会に出たときに大きな武器になる。孤立せず、積極的に人と関わり、雑談からでもつながりをつくること。それが、大学生に求められる姿勢なのだと感じました。
プロフィール
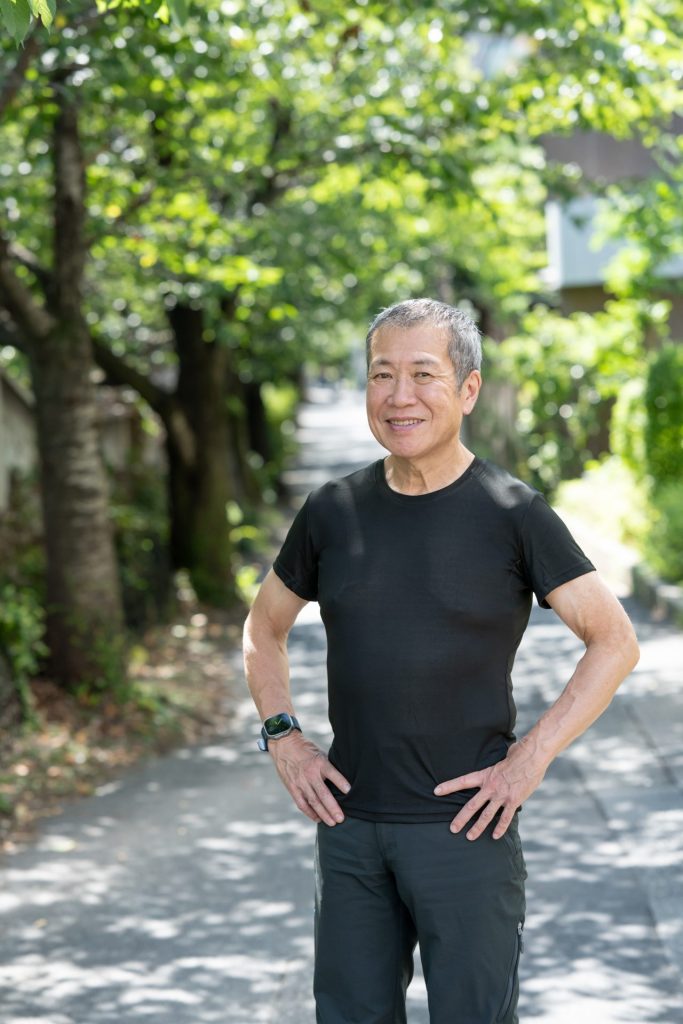
佐々木俊尚(ささき・としなお)
1961年兵庫県生まれ。早稲田大学政治経済学部中退。毎日新聞記者、『月刊アスキー』編集部を経て、2003年よりフリージャーナリストとして活躍。ITから政治、経済、社会まで幅広い分野で発言を続ける。現在は東京、軽井沢、福井の3拠点で、ミニマリストとしての暮らしを実践。著書に『レイヤー化する世界』(NHK出版新書)、『そして、暮らしは共同体になる。』(アノニマ・スタジオ)、『時間とテクノロジー』(光文社)など。
https://x.com/sasakitoshinao
関連記事
-
保護者におすすめ! 
【業界のプロに聞く】学生の住まい選び、2026年の新常識。「家賃の安さ」だけで選ぶと後悔する? 退学リスクも下げる“正しい投資”とは。
2026.02.05
-
高校生におすすめ! 
「生産性のない時間」こそが、自分を助けてくれる。——文筆家・岡田悠が語る「人生という旅」の歩きかた【連載・夢中人 Vol.11】
2026.01.19
-
高校生におすすめ! 
「人生は『泥縄』や。とりあえず引っ張れ!」先が見えない時代こそ面白く。―高木 秀章さん(塾長・学習塾経営)【連載・夢中人 vol.10】
2025.12.23
-
保護者におすすめ! 
悲観ではなく可能性を──大学全入時代に保護者が持つべきまなざし
2025.11.17