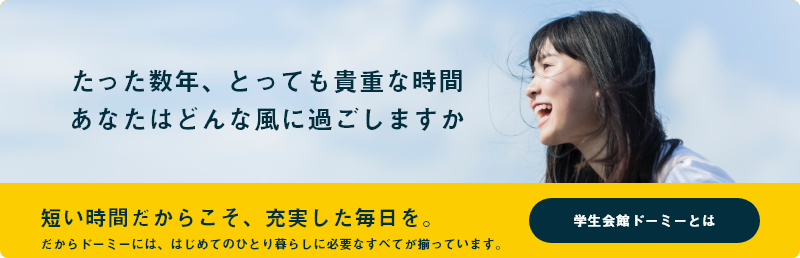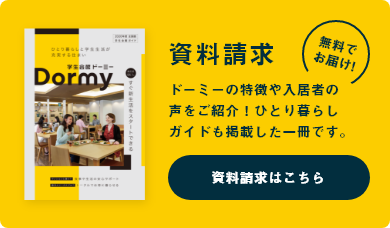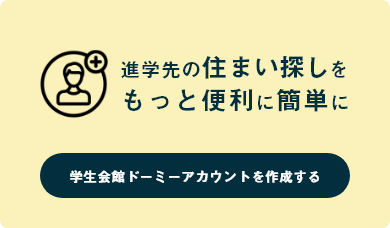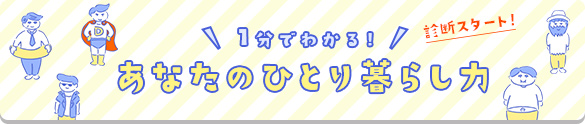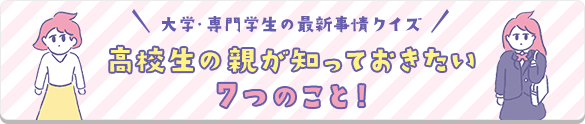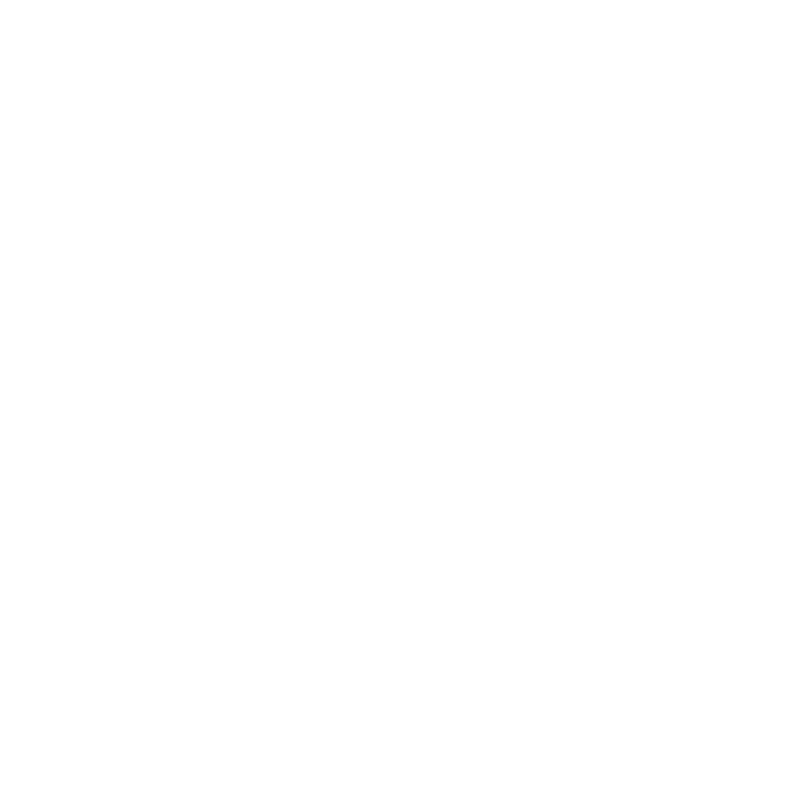【対談】「奨学金、マイナスからのスタートを変えたい」若者の未来を支える新しい選択肢

「それって、おかしくないですか?」
そう声を上げ、奨学金返済を支援する新しい仕組み「奨学金バンク」を立ち上げたのが、アクティブアンドカンパニー代表の大野順也さんです。
人材・組織の分野で20年以上のキャリアを持つ大野さんは、なぜ奨学金支援に取り組むことになったのか。この仕組みは、学生や保護者にとってどんな意味を持つのか。お話を伺いました。
⏱この記事は約9分で読めます
「35歳なのに、まだ奨学金返してるんです」
——奨学金バンクを始めたきっかけを教えてください。
大野さん: 今から6年ほど前、当時35歳の知人が「僕、まだ奨学金返してるんです」と言ったんですね。
その時、私は45歳でした。大学卒業から13年経っても返済が続いているという事実に、正直驚きました。「え、まだ返してるの?」って。
——13年も。
大野さん: そうなんです。それで調べてみたら、今は奨学金を返し終わるのが40歳前後、場合によっては40歳を超えても返している人がたくさんいる。
大学生の2人に1人、約55%の人が奨学金を借りていて、平均300万円前後を約15年かけて返しているんです。
——新入社員の半分が、借金を抱えているということですね。
大野さん: そうなんです。弊社では教育研修事業も行っており、毎年春に新入社員研修を行っています。目の前で研修を受講している新入社員が30人、40人いて、その半分以上が借金を返すところから社会人生活をスタートしているんだなと思ったら、「これは大きな社会課題だな」と感じたんです。
なぜかというと、マイナスからのスタートなんですよ。借金を0に戻すことが第一目標になってしまう。
どんどん稼いで生活を豊かにしようとか、やりたいことをやろうという前向きな感覚より、「まず借金を返さなきゃ」という後ろ向きのスタートになってしまうのです。
——やる気も、元気も出ないですよね。
大野さん: そうなんです。社会に対する期待とか希望、夢みたいなものが薄らいでしまうんじゃないかと。
私たちは新入社員研修で「やる気を出して頑張っていこう!」と言ってるわけですけど、その前に生活基盤とか生活インフラを支援できるようなことをやった方が、もっと人や組織が活性化するんじゃないかと思ったんです。
それが、奨学金バンクを始めたきっかけです。

なぜ企業が学生の奨学金を返すのか
——大野さんは、人材・組織の分野で長くお仕事をされてきたんですよね。
大野さん: はい。パソナで営業責任者、デロイトトーマツコンサルティングで人事コンサルタントを経験して、2006年に今の会社を立ち上げました。
ずっと「人事・組織・人材」という領域で仕事をしてきたので、奨学金問題も人材の視点から見えてきたんです。
——というと?
大野さん: なぜこれほど多くの人が大学に行くようになったのか。それは、企業側——つまり私たち事業主の責任でもあると思っているんです。
——企業の責任?
大野さん: ほとんどの会社が、大卒を中心に採用していますよね。高卒や専門卒を中心に採るという会社は、あまり多くない。
つまり、企業が学歴のインフレを招いているわけです。大学に行かないと、東京で一人暮らしをして食べていくのが難しい社会を作ってしまっている。
——確かに。
大野さん: 大学に進学することが悪いわけではないんです。そうすることで優秀な人材が育つという面もある。
でも、その経済負担を学生だけが背負っていて、返還しやすい仕組みが整っていない。学費は過去10年で倍近くになっているのに、世帯年収はほぼ横ばいです。
そのような状況の中で、今後も優秀な人材を確保したいのであれば、企業側が返還を支援すべきじゃないか——そう考えたんです。
奨学金バンクの仕組み
——奨学金バンクは、具体的にどういう仕組みなんですか?
大野さん: シンプルに言うと、「奨学金返還を支援してくれる企業への就職をサポートする」仕組みです。
——企業は、なぜ学生の奨学金を返してあげるんですか?
大野さん: 企業側にもメリットがあるからです。
まず、奨学金を借りてまで学校に通った人は、就学意欲・就業意欲が高いんですよ。そういう人材を確保できるというのが一つ。
それから、経済的に支援した社員は、会社に対する帰属意識が高くなり、定着しやすい。長く働いてもらえる。
さらに、「奨学金返還を支援している会社」であることが、SDGsに取り組む企業としてのブランディングにつながり、採用力や企業イメージの向上も期待できるんです。
——学生にとっても企業にとっても、メリットがあるんですね。
大野さん: そうです。そして、私たちの仕組みの特徴は、企業が奨学金バンクに参画するという支援だけではなく、寄付による支援もあるという点にあります。
——寄付?
大野さん: はい。企業や個人の方からの寄付も集めています。
その寄付金を、奨学金バンクを通じて就職した方に割り当てることで、企業が単独で支援するより多くの支援ができる。私たちと組んだ方が大きなムーブメントを生み出せるるんです。
——みんなで支え合う仕組みなんですね。
大野さん: そうです。だからこそ、これを「社会インフラ」にしたいと思っています。

「よく分からない」という声にどう答えるか
——ネットで検索すると「奨学金バンク 怪しい」という声もあるようですが。
大野さん: それは当然だと思います。新しい仕組みですし、お金が絡むことですから。
ただ、私たちだけがやっていたら確かに怪しいかもしれませんが、日本学生支援機構という国の機関、それから三井住友信託銀行という日本最大手の信託銀行と、三位一体で取り組んでいます。
——信託銀行?
大野さん: お金の管理は三井住友信託銀行にお願いしていて、信託財産として管理していただいています。安全性が高く、透明性のある仕組みです。
私たちは、あくまで事務代行をしているだけ。そう考えていただければと思います。
——「全額返してもらえる」と勘違いしている人もいるのでは?
大野さん: そこは誤解のないようにお伝えしたいんですが、奨学金バンクは「奨学金返還を支援してくれる企業への就職をサポートする」仕組みです。
就職が決まらなければ、支援は受けられません。
——なるほど。
大野さん: もちろん、企業によっては3年で終わらず、継続的に支援してくれるところもあります。また、基本パッケージは「毎月1万円×3年間=36万円」ですが、先ほどお伝えしたとおり、寄付が集まるほど割り当て可能な金額が増えるため、返還支援期間を延長することができます。実際に、サービス開始初年度である2024年度分から割り当て金が発生し、1人当たり1カ月の支援期間の延長も実現しています。
全額ではないけれど、確実に負担は軽くなります。

18歳で300万円の借用書にサインする、ということ
——これから奨学金を借りる高校生や保護者の方に、伝えたいことはありますか?
大野さん: まず、奨学金そのものは決して悪いものではないということです。就学・就業を促進するものですから。
ただ、一つ考えてほしいのは、18歳の高校生が何百万円もの借用書にサインをするということの重さです。
——確かに。
大野さん: その時点で、大学を卒業できるかどうかわからない。就職できるかどうかもわからない。仮に就職できたとしても、返還できるだけのお給料がもらえるかもわかりません。
それなのに、何百万円もの借金を背負わせる。これって、すごく横暴だと思いませんか?
——言われてみれば…。
大野さん: だから、奨学金を借りる段階で「こういう選択肢がある」と知っておくことがすごく重要なんです。
奨学金を借りたら、まず奨学金バンクに登録して情報を見ておくだけでいい。「出口がある」と知っているだけで、安心感が全然違うと思うんです。
——「奨学金が怖い」と感じて、進学を諦める人もいますよね。
大野さん: それが一番もったいない。奨学金が怖くて学校に行かないことで未来が閉ざされるなら、私は行った方がいいと思います。
学校に行って、新しい道を開く。その先の解決策は、奨学金バンクも含め、どんどん広がっているんです。
国も2021年に「奨学金返還支援制度」を創設し、企業への普及を進めています。この4年で、制度を導入する企業は全国的に増えており、昔とは違う、新しい選択肢があるんだということを、ぜひ知っていただきたいです。
大学を辞める7万人のことも
——大学を中退する学生さんへの支援も考えているそうですね。
大野さん: はい。実は、毎年7万人の学生が大学を辞めているんです。
もちろん、より自分に合った専門課程に進学するために辞める人もいますが、経済的な理由などで辞めざるを得ない人も一定数います。
——その人たちも奨学金は返さないといけない。
大野さん: そうなんです。しかも、大学の就職支援が十分に行き届かないため、アルバイトや派遣、契約社員で働き始めることが多い。
奨学金の返還は、最後の振込から半年後にスタートします。この半年の間に正社員として就職できるかどうかで、その後のキャリアが大きく変わってしまう。
——ファーストキャリアが大事なんですね。
大野さん: はい。だから、そういう方たちにも知っていただいて、正社員として働くチャンスをつかんでほしいと思っています。
0.5合目。でも確実に前へ
——今、奨学金バンクはどのくらいまで来ているんですか?
大野さん: 0.5合目くらいですね。(笑)
——まだまだこれからなんですね。
大野さん: そうです。まずは、大学生の半数が「奨学金バンク」を知っている状態を作りたい。
もっと手前の目標で言うと、東京都内の大学生の3割くらいが知っている状態ですね。
——最終的な目標は?
大野さん: 日本の奨学金総額は9兆5000億円あります。そのうちの1割、1兆円がこの仕組みを通じて返還される規模にしたい。
そうなれば、「民間企業が国の奨学金制度を支えている」と言えると思うんです。
——社会インフラですね。
大野さん: はい。一企業がやっている単なるサービスではなく、いろんな人が参画して、みんなで支え合うインフラ。それがこの事業の目的であり、目標です。

学びを諦めないために
——最後に、ドーミーラボを読んでいる学生さんや保護者の方にメッセージをお願いします。
大野さん: まず学生さんには、「奨学金を返すときの一つの手段として、奨学金バンクがあるよ」ということを知っていただきたいです。
使うか使わないかは、もちろん皆さん次第です。でも、選択肢があることを知らないことで不幸になることもある。だから、ぜひ知っておいてください。
そして、この仕組みがどう大きくなっていくのか、見守っていただければと思います。必ず、巡り巡って皆さんに返ってくるサービスに発展していきますから。
——保護者の方には?
大野さん: 奨学金を借りさせることに、申し訳ないと感じている親御さんも多いと思います。
でも、学ぶことで広がる未来の方が、ずっと大きい。そして今は、返還を支える仕組みが社会全体で広がっています。
お子さんと一緒に、こういう選択肢があるんだということを調べて、話し合っていただけたらと思います。
——ありがとうございました。
編集後記:支え合う社会への第一歩
取材を終えて改めて感じたのは、奨学金バンクは単なる「返済支援サービス」ではないということです。
学生も、企業も、すでに返済を終えた人も、みんなが参加できる。1000円の寄付も、企業の支援も、等しく次の世代を支える力になる。
「社会人生活は、借金返済からのスタートじゃなくていい」
その当たり前を、当たり前にするために。
奨学金バンクの挑戦は、まだ始まったばかりです。
奨学金バンクをもっと詳しく知りたい方は
取材協力
アクティブアンドカンパニー株式会社
代表取締役社長 大野順也さん