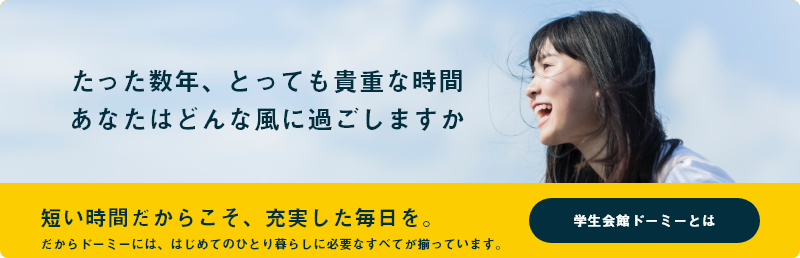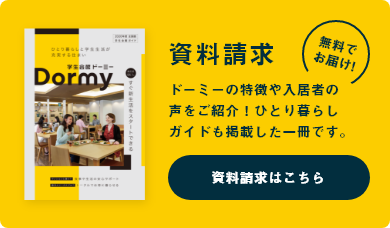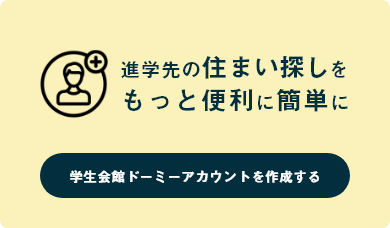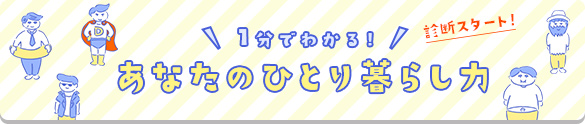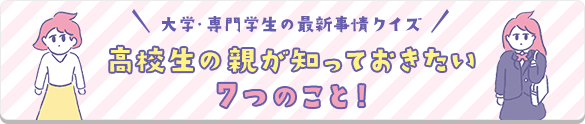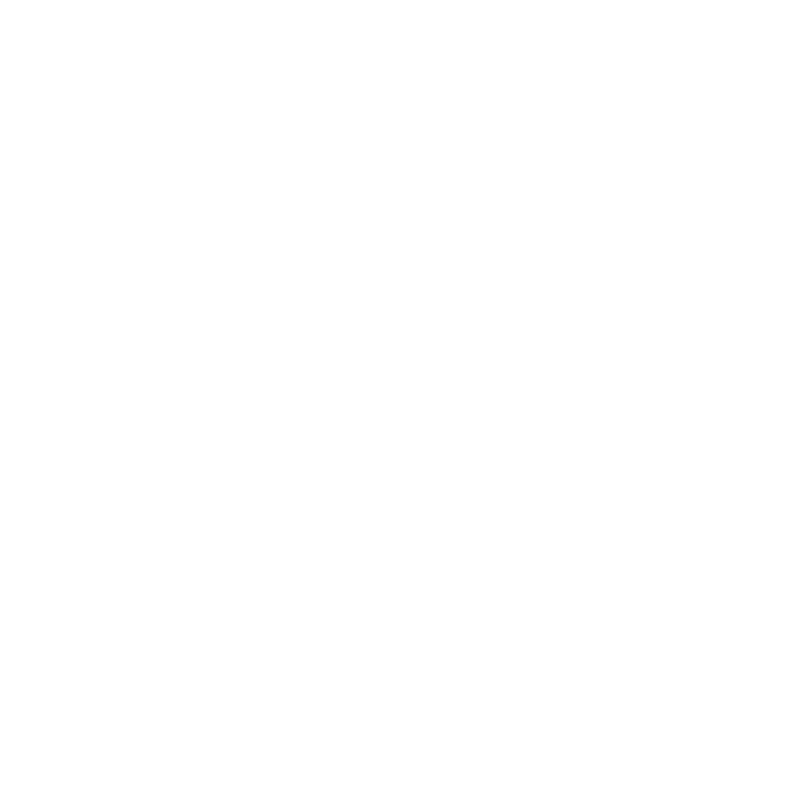悲観ではなく可能性を──大学全入時代に保護者が持つべきまなざし
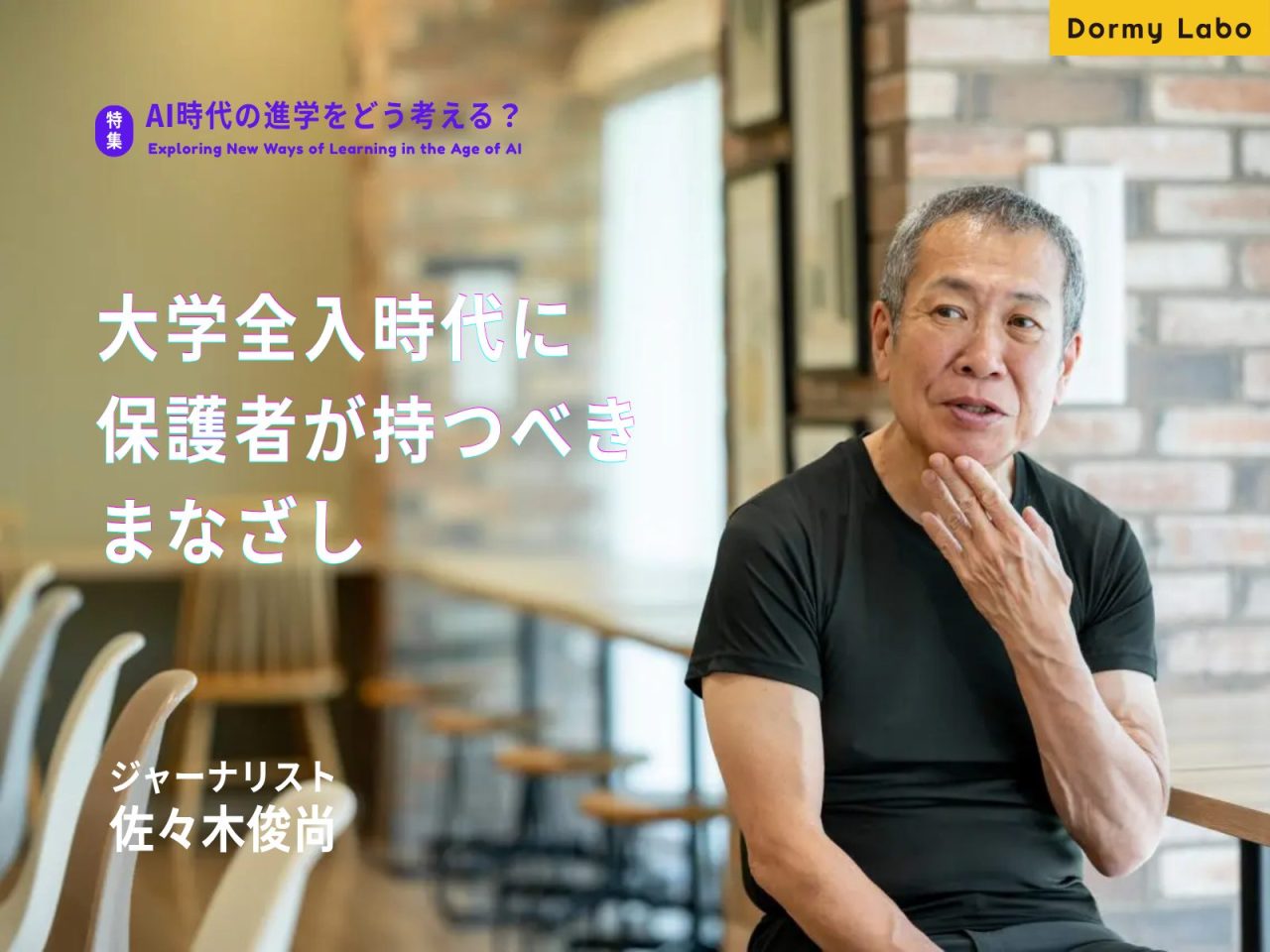
学歴の価値が揺らぐなかで、保護者は子どもたちの進路をどう支えればよいのでしょうか。
社会やテクノロジーの変化を読み解くジャーナリスト・佐々木俊尚さんが、“悲観ではなく可能性を見る視点”の大切さを語ります。
⏱この記事は約3分で読めます
大学全入時代における学歴の価値
「去年ぐらいから大学全入時代になったんです。会議の大学であれば誰でも入れるようになってきている。そうなると“大卒”という学歴の価値は、一部の上位校を除いて、ほぼ消滅するんじゃないかと思います」
かつて大卒という学歴は就職活動での「足切り」として強い意味を持ちましたが、今後は一部の大学を除き、その効力が失われていくと佐々木さんは指摘します。
「AIが今すごい勢いで進化していて、一般事務は完全に代替されていくでしょう。そうなると事務職の給料は下がっていく。むしろ建設や現場の仕事は簡単にはロボットに置き換えられない。賃金は上がりつつあり、遠からずホワイトカラーと逆転する時代が来ると思うんです」
大学進学が「安定した事務職に就くための手段」という時代は終わりを迎えつつあります。これからの大学の役割は、知識の習得よりも人脈やコミュニティを築く場へとシフトしていくといいます。
保護者世代とのギャップ
「今の大学生の親世代は50代ぐらいが中心。昭和から平成にかけて青春時代を過ごした彼らの常識は、今の時代には合わなくなっています。どうしても古い考えを子どもに押し付けてしまう。そのズレは学生にとって大きな負担になるでしょう」
かつては「1つの会社で出世する」ことが理想とされました。しかし今は「専門性を持ち、転職を自由にできること」が重要視される時代。管理職を敬遠する若者も増えています。
「親の世代が持つ“出世が成功”という価値観をそのまま子どもに当てはめるのは危険です。社会の前提そのものが変わってきているのですから」
悲観に偏らないことが大事

「90年代に青春を過ごした保護者は、“日本はずっと停滞している”という感覚を持っているかもしれません。でも実際には2020年代に入ってから日本は持ち直しつつある。経営者の世代交代が進み、海外資本の流入も増え、前向きな変化が生まれているんです」
「国内メディアを見ると停滞しているように映るけれど、海外メディアやアナリストの評価は違う。“日本は今いいんじゃないか”と語る人は少なくない。だからこそ保護者は、過去の感覚に縛られず、現実をフラットに捉えることが大切です」
子どもに必要以上の悲観や不安を植え付けず、むしろ新しい可能性を見据えながら支えていく。佐々木さんはその姿勢を、今の時代に保護者が持つべき最大のポイントとして語りました。
編集部まとめ
進路を選ぶ過程で、子どもは保護者から大きな影響を受けます。しかし、保護者世代が歩んだ時代と今とでは、社会の前提は大きく異なります。古い常識を押し付けるのではなく、変化を理解し、希望を持って子どもを支えること。これが、佐々木さんが語る「保護者が持つべき新しい視点」だと感じました。
プロフィール
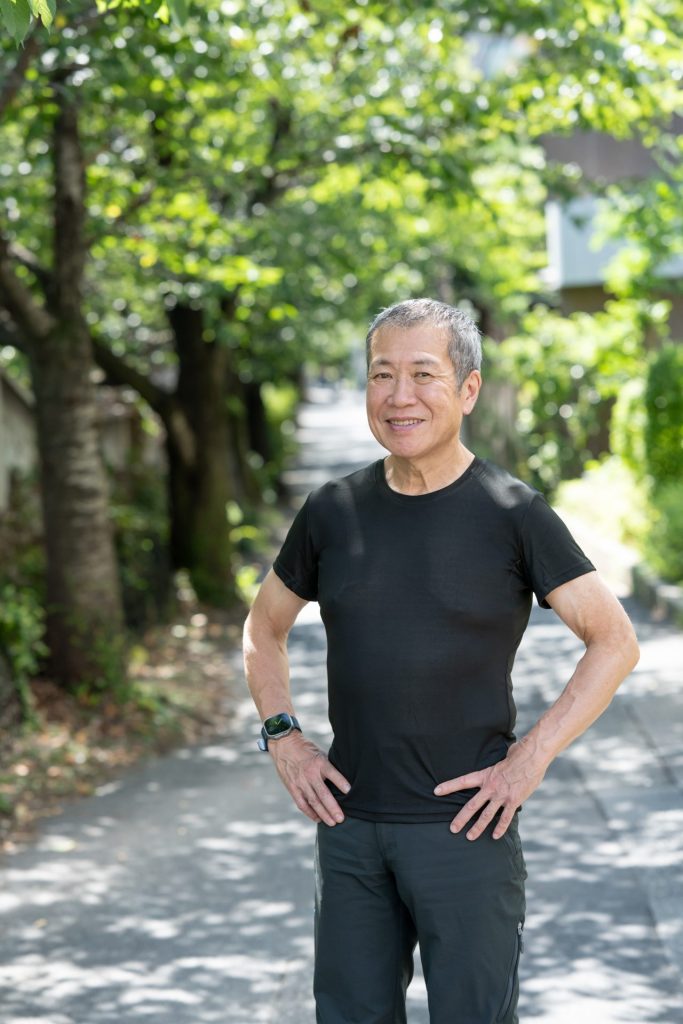
佐々木俊尚(ささき・としなお)
1961年兵庫県生まれ。早稲田大学政治経済学部中退。毎日新聞記者、『月刊アスキー』編集部を経て、2003年よりフリージャーナリストとして活躍。ITから政治、経済、社会まで幅広い分野で発言を続ける。現在は東京、軽井沢、福井の3拠点で、ミニマリストとしての暮らしを実践。著書に『レイヤー化する世界』(NHK出版新書)、『そして、暮らしは共同体になる。』(アノニマ・スタジオ)、『時間とテクノロジー』(光文社)など。
https://x.com/sasakitoshinao