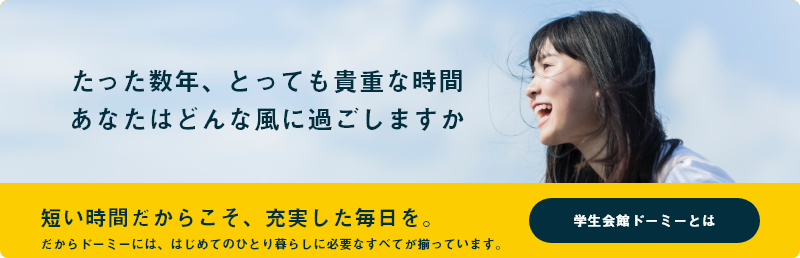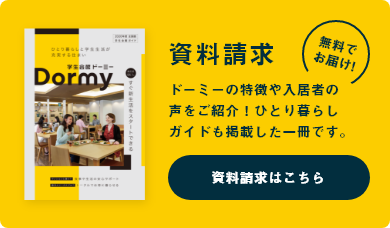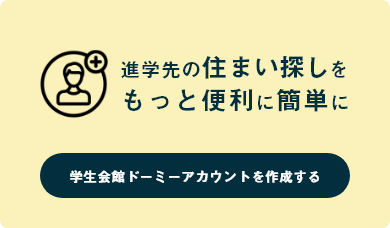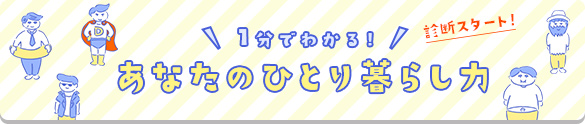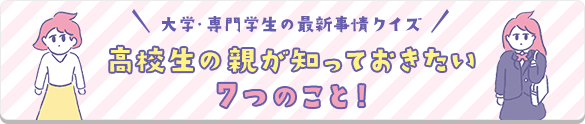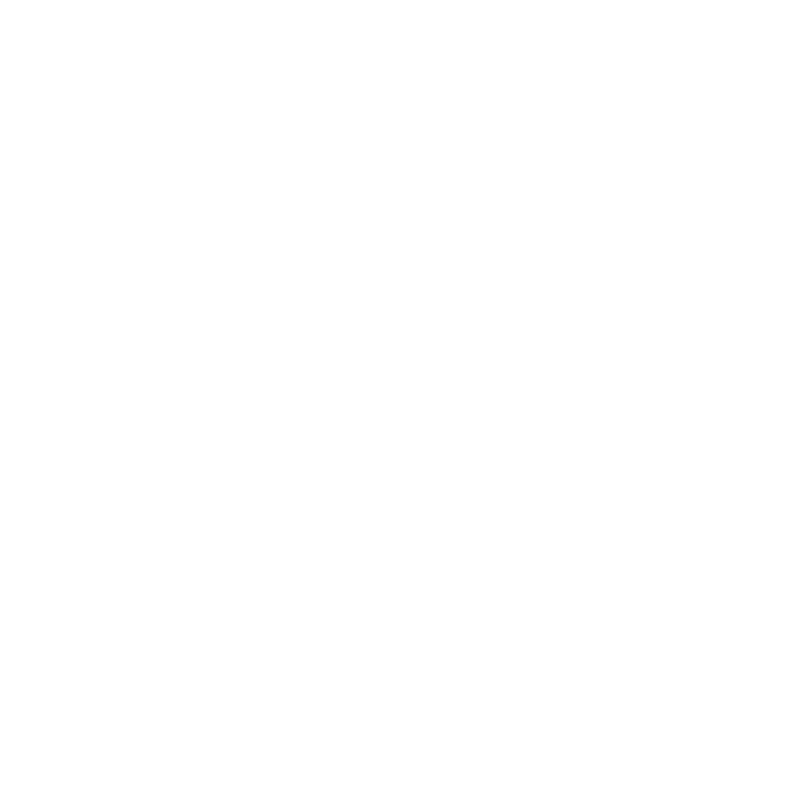模試の結果・判定が悪かった時の具体的対策|受験逆転合格を目指す方法

「志望校がE判定だった…」
受験生なら誰もが一度は経験するこの現実。特に志望校を高く設定している方ほど、模試の結果に一喜一憂することでしょう。
しかし、模試の結果が悪かったからといって、すぐに志望校を諦める必要はありません。適切な対策と効率的な学習方法を実践することで、逆転合格の可能性は十分にあります。
本記事では、模試の結果や判定が悪かった時の具体的な対策方法を解説します。
⏱この記事は約6分で読めます
模試の判定とは?まずは冷静に結果を分析しよう
そもそも模試の判定って?
模試ではテストの素点や偏差値以外に、選択した志望校に合格できる可能性についての評価が行われます。一般的にA~Eの5段階で表されることが多く、以下のような意味を持ちます:
- A判定(合格可能性80%以上):今の実力を維持すれば合格の可能性が高い
- B判定(合格可能性60%程度):もう少し実力を上げれば合格圏内
- C判定(合格可能性40%程度):合格可能性は五分五分
- D判定(合格可能性20%程度):かなりの努力が必要
- E判定(合格可能性20%未満):現状では厳しい状況
※模試を実施する団体によっては5段階評価でない場合や、別の表現を用いる場合もあります。
しかし、この判定はあくまで「現時点での」合格可能性を示すものです。判定が悪かった場合でも、残された時間でどれだけ成長できるかが重要なのです。
模試の結果を正しく理解する
模試の結果には、判定以外にも多くの情報が含まれています。
- 科目別・分野別の正答率
- 設問別の難易度と正誤
- 志望校のボーダーライン
- 全受験者の中での偏差値・順位
これらの情報をしっかり分析することで、自分の弱点や伸ばすべき分野が明確になります。特に、正答率が低い分野や、難易度の低い問題で間違えている部分に注目しましょう。
D・E判定からでも逆転合格は可能!
D判定やE判定が出ても、諦める必要はありません。実際に、模試でD判定やE判定だった受験生が、本番で合格するケースは珍しくありません。
逆転合格を目指すには、以下の3つを基本方針としておさえておきましょう。
- 弱点を明確にし、集中的に対策する
- 基礎力の徹底強化
- 効率的な学習方法の導入
これらのポイントを踏まえ、具体的な対策を見ていきましょう。
模試の結果が悪かった時の具体的対策10選
①模試の結果を徹底分析する
まず、模試の結果を科目別・分野別に分析しましょう。特に以下のポイントに注目します。
- どの科目のスコアが低いか
- 各科目の中でどの分野・単元が弱いか
- 基礎的な問題で間違えているか、応用問題で間違えているか
この分析をもとに、優先して対策すべき科目や分野を特定します。限られた時間を有効に使うために、この分析は非常に重要です。
②志望校の出題傾向を研究する
志望校の過去問や、出題傾向の分析資料を入手し、詳しく研究しましょう。多くの大学では、特定の分野や形式の問題が繰り返し出題される傾向があります。志望校が重視する分野を集中的に強化することで、効率よく得点力を上げることができます。
③基礎の再確認と反復練習
模試の結果が悪い場合、多くは基礎的な部分の理解が不十分であることが原因です。特にD・E判定の場合は、応用問題よりも基礎の強化が優先です。
- 教科書の基本事項を再確認
- 基礎問題集を繰り返し解く
- 公式や定理、基本用語の完全暗記
基礎が固まれば、応用問題への対応力も自然と向上します。
④学習計画の見直しと再設定
残り時間を考慮した、現実的かつ効果的な学習計画を立て直しましょう。
- 1日・1週間単位での具体的な計画を立てる
- 弱点分野に多くの時間を配分する
- 定期的な復習時間を確保する
- 小テストや模試などの確認ポイントを設定する
計画を立てるだけでなく、実行状況を日々チェックすることも重要です。
⑤効率的な学習法の導入
限られた時間で最大の効果を得るために、効率的な学習法を取り入れましょう。
- 集中と休憩のバランス:たとえば25分間集中して勉強し、5分休憩するというサイクルを繰り返すと、集中力が長続きします。
- 自分で思い出す練習:教科書やノートを読み返すだけでなく、いったん閉じて内容を自分の言葉で思い出す練習をすると記憶に定着しやすくなります。
- 計画的な復習:一度学んだことを1日後、3日後、1週間後と間隔を空けて復習すると忘れにくくなります。
- 誰かに教えるつもりで勉強する:学んだ内容を友達や家族に説明する(または説明するつもりで整理する)と理解が深まります。
特に「ただ読む」だけでなく「自分で書く」「声に出す」「説明する」といった形で学習内容を外に出す(アウトプットする)勉強法は、知識の定着に非常に効果的です。
⑥学習環境の最適化
集中できる環境づくりも重要な要素です。
- スマホなどの誘惑を遠ざける
- 学習に適した明るさと温度を保つ
- 必要な参考書や文具を手の届く範囲に配置する
- 図書館や自習室など、集中できる場所を活用する
⑦模試や過去問の解き直し
間違えた問題の解き直しは、最も効果的な学習方法の一つです。
- なぜ間違えたのかを分析する
- 正解までの思考プロセスを理解する
- 類似問題に取り組み、応用力を身につける
解き直しの際は、単に答えを覚えるのではなく、解法のプロセスを理解することが重要です。
⑧メンタル面のケア
受験勉強は精神的にも負担が大きいもの。メンタル面のケアも忘れないようにしましょう。
- 適切な休息と睡眠を確保する
- 適度な運動で気分転換する
- 小さな成功体験を積み重ねるよう心がける
- 必要に応じて友人や家族、先生に相談する
受験生のストレスマネジメントについて、目白大学新宿キャンパス学生相談室の公認心理師さんにお聞きした記事があります。こちらもぜひ合わせてご覧になってください。
⑨併願校の再検討
志望校へのチャレンジを続けながらも、併願校の選択肢を広げることも検討しましょう。
- 学びたい分野・学部が似ている大学
- 偏差値が自分の実力に近い大学
- 地理的条件が似ている大学
複数の選択肢を持つことで、精神的な余裕も生まれます。
⑩専門家のアドバイスを活用する
一人で悩むよりも、専門家のアドバイスを積極的に求めましょう。
- 学校の先生に弱点分析と対策を相談
- 予備校の講師に効率的な学習法を尋ねる
- 先輩や合格者の体験談を参考にする
特に模試を実施している予備校では、結果に基づいた具体的なアドバイスをもらえることがあります。
模試の結果に一喜一憂せず、着実に実力を伸ばそう
模試の結果は、あくまで現時点での実力を測るものです。判定が悪かったとしても、それは「今後どう対策すればよいか」を示す貴重な情報源として活用しましょう。
基礎力の強化、効率的な学習法の導入、メンタル面のケアなど、紹介した対策を実践することで、模試の結果を大きく覆すことは十分に可能です。
大切なのは、結果に一喜一憂するのではなく、自分の弱点を知り、それを克服するための具体的な行動を継続することです。逆転合格を目指して頑張りましょう!